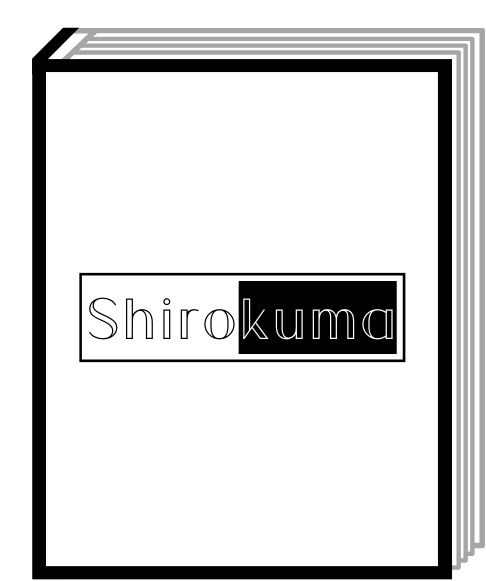民泊と旅館業
民泊と旅館業
ややこしいですね…。それもそのはず、「民泊」という言葉は法律上定義された言葉ではないんですね。
一般的に民泊とは「住宅や共同住宅の全部又は一部を使用して宿泊サービスを提供する施設」のことを指しています。
よく「民泊は営業日数に180日の制限がある」とか、「旅館業は許可が必要だけど営業日数に制限はない」といったことを聞きますが、本来はこの180日制限の有る民泊も、旅館業も同じ「民泊」という言葉の中に含まれるのかもしれません。
ですが、民泊といえば180日制限の有る宿泊施設、旅館業と言えば180日制限のない宿泊施設、という認識が一般的に広まっているような気もします。
このあたりの解釈はさておき、今回は、この180日制限がある民泊と、営業日数に制限のない旅館業の許可を取得した民泊、それぞれの特徴をざっくりとご説明します!
1.法律上の位置付け
180日制限のある民泊は、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」という法律に基づいて運営されます。
この法律により、年間で提供できる宿泊日数が180日以内に制限されているのが特徴です。
民泊を行う住宅宿泊事業者は区、市町村などに届け出を行う必要があります。
届出をする前に、管轄の保健所、消防署等へ事前相談を行い、施設に必要となる「設備の要件」や近隣住民への事前説明などの「必要な手続」を確認します。
とはいえ、用途地域や地区計画、さらには建築基準法による制限も受けるため、実際には実に様々な法令の要件を満たしていることが求められます。
保健所と消防に確認したから全部OK、というわけではないんですね。
一方、180日制限のない旅館業許可が必要な民泊では、施設の形態や規模に応じて以下の業態に分類されます。
①旅館、ホテル営業:伝統的な旅館やペンション、ホテルなど。
②簡易宿所営業: カプセルホテルやゲストハウスなどの簡易な宿泊施設。「旅館、ホテル営業」との大きな違いは、一つの部屋に多数のグループを宿泊させる形態であること。
③下宿営業: 長期滞在者向けの下宿施設。
これらの施設は全て、開業時に保健所の「許可」を取得する必要があり、衛生管理や防火設備の設置など、180日制限のある民泊と比べると厳しい規制をクリアしなければなりません。
特に気を付けなければならないのは建築基準法です。
なぜなら、一般住宅や共同住宅として建築された建物を旅館という用途に変更するとなると、容積率の計算方法が異なる(旅館の方が厳しい!)ため、指定の容積率をオーバーしてしまい、建築基準法令違反で「旅館業ができない」可能性もあるのです。
せっかくいい物件が見つかり、衛生設備、消防用設備もOKと思っていても、そもそもこの建物で旅館をすることが「出来ない」という恐ろしい可能性がありますので注意が必要です。
2.消防法の適用
住宅宿泊事業法上の民泊も、旅館業法上の民泊も、消防法ではどちらも宿泊施設(5項イ)として扱われるため消防法の規制として差異はありません。
どちらも、宿泊する人数や施設の構造によって、消防用設備の設置義務が発生します。
また、設備以外にも、一定人数以上を宿泊させる場合には、防火管理者の選任や消防計画の作成が必要であったり、カーテン類を防炎物品にしなければならないなどの規制もあります。
3.まとめ
180日制限のある住宅宿泊事業法上の民泊か、営業日数に制限のない旅館業法上の民泊、どちらを選ぶかは、運営者が提供するサービスの内容や規模に応じて決まりますが、それぞれの違いを理解した上での計画が大切です。
物件契約をした後に「実は許可が取れないことが分かった…」「180日営業できると思っていたら、用途地域の制限により土日しか営業できなかった…」といったことを避けるためには事前の確認がとても大切です。
民泊に興味が出てきたら、その際はしろくま行政書士事務所に是非ご相談ください!
専門家が迅速かつ確実に対応いたします!